こんにちは、しゃんはいさくらです。
中国では2021年の秋から「双減政策」が施行されました。
この政策、私たちの生活にそれなりの変化をもたらしたので、周りの状況を紹介しながら、「双減」についての私見を書いておこうと思います。
双減政策とは?
日本では「中国版ゆとり教育」などと言われている中国の「双減政策」。
百度百科に掲載されている中国政府のオフィシャルな説明ではこのように書かれています。
“双减”指要有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。
※百度百科より
つまり、
義務教育段階にある学生の宿題負担と校外学習の負担を減らすこと
を指しています。

この政策は中央弁公庁、国務院弁公庁が連名で出すほどの強い強制力がある政策で、これを受けて各地方政府で更に細かい規定が制定、運用され、現在に至ります。
上海の状況
上海では今年の8月24日に、『義務教育段階の学生の宿題と校外学習負担を更に軽減することに関する実施意見』が公布され、今後約1年の時間を使って現状を改善し、2023年までに学校教育の品質を顕著に向上させていくことが明確にされました。
政策を通じて改善していきたい内容は次のとおり。
・宿題の量と時間のコントロール
・学内放課後サービスの展開
・校外学習機関の規範化
・学生の宿題と校外学習の負担軽減
・家庭の教育支出と親の負担軽減
ホンマかいな!?とツッコミたくなるような内容ばかりですが、我が子の事例を参考にそれぞれを説明していきます。
宿題の量と時間のコントロール

【基本ルール】
小学1、2年生には書面宿題(書き取りなど)を出さないこと。
3~5年生は60分以内で終われる量にすること。
中学生(6~9年生)は90分以内で終われる量にすること。
【現状】
下の子(5年生)は国・数・英でそれぞれ20分ずつを想定した宿題が出されています。
各教科で1~2項目程度です。
但し、どの先生も明言してますが
「5年生でこれだけの宿題では絶対に足らない」
とのことで、 余裕のある人は との言い方で別の宿題が課される時があります。
昨年までは1教科について少なくとも3項目の宿題があったので、表向きの量は確かに減った感があります。
ただ実際は、これまで家でやれば良かった宿題の一部が“课内作业”となり授業中に終わらせる形になったので、総量としてはそれほど減ってないかも知れません。
元々ウチの子が通う学校はガツガツ勉強させる学校ではなく、以前の量でも学校で済ませてしまう子が少なくありませんでした。
ウチの子は友だちとおしゃべりがしたいのとのんびりタイプなので、これまで学校で済ませて帰って来たことは一度もなく、「双減政策」が始まった今学期もそれは同様で、毎日9時くらいまでダラダラとやってます。
上の子(8年生:中2に相当)は日によって宿題の量にバラツキがあり、遅くまでかかる日と帰宅前に学校で済ませている日があります。
1つの教科に1~2項目程度の宿題で見た目の量はそれほど多く感じませんが、中学生なので主要3教科の他に物理の宿題が加わっています。
上の子くらいの年齢になるとさすがに要領も心得てて自分なりに工夫している(やるところ、抜くところを調節して睡眠を確保)様子ですし、何よりこっちの言うことを聞かない年齢なので、半ば放ったらかしです。
結局、宿題問題は子どものやる気や要領に関わる部分が大きく、量や時間で線引きするのは本質からズレてるような気もします。
まぁ、これが中国のやり方だと言ってしまえばそれまでですけれども。
学内放課後サービスの展開
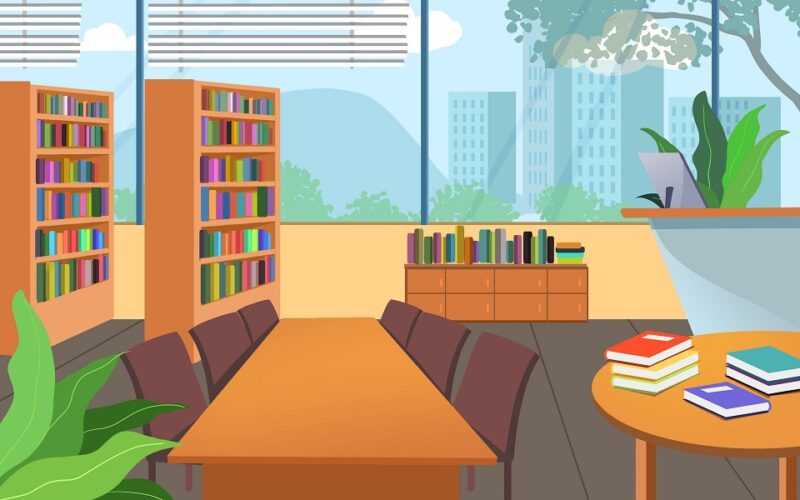
【基本ルール】
放課後のサービス時間(2時間以上)、サービス品質、サービス品目拡大に努める。
放課後サービスの終了時間は現地の一般的な退勤時間より早くならないこと。
【現状】
ウチの子が通う学校は以前から“晚托”と呼ばれる自習時間があり、下校時間は午後4時10分以降で、小学校1年生から順番に5分刻みでお迎えに行くルールが運用されています。
希望者に対して夕方6時頃まで預かってくれるサービスがあり、基本的に図書館での自習がメインです。
放課後サービスについては、新しい政策が出た後も学校側の運用に変化はありません。
敢えて変わった点を挙げると、以前は遠足やテストなどで早上がりする日がありましたが、政策後は、遠足から帰って来た後に“晚托”を学校で過ごしてから(本を読んだりして待機する)、いつもと同じ時間に下校するようになりました。
我が家は元々放課後サービスを必要としていないですし(義母のおかげです)、これについては政策前も政策後も変化なく過ごしています。
校外学習機関の規範化
学生の宿題と校外学習の負担軽減
家庭の教育支出と親の負担軽減
.jpg)
私たちへの影響が大きく、いろんな人の生活が一変してしまった政策です。
私の周りで起こったことや個人的な所感は次回書きたいと思います。
上の子が正論を返してきた
子どもたちの「双減政策」への反応は様々です。
下の子は「双減政策」を真に受けて、宿題を勝手に手抜きするようになり、先生からご指導を頂くハメに。
5年生の割にはまだまだ幼稚なところがある子です。。。
一方で中学生である上の子たちの年齢になると、冷静にこの政策を分析しています。
[st-kaiwa1]「双減」って言うけど、今減らしても結局は高校でやらなきゃダメじゃん?だって大学入試の試験問題が簡単になるわけじゃないんだから。[/st-kaiwa1]
ですって。
まぁ、至極まっとうな答えですよね。
そうなんですよ、この「双減政策」の対象はあくまでも
義務教育段階の子どもたちに対するもの
であって、今、どんなに宿題や校外学習の負担を減らされたところで、数年後にやってくる高校受験や大学受験制度が変わらない限り、それに耐えうる学力が必要であることに変わりはないんです。
「双減政策」が厳しく実施されれば実施されるほど、
できる子とできない子との差や、
教育にお金や時間をかけられる家庭とそうでない家庭の差が広がるだけ。
この辺りのつぶやきは、上でも書いたとおり校外学習の規制問題と合わせて次回書きますが、簡単に言えば、チャイナドリームを実現したい一方で、党を脅かすような存在が出てくるのを恐れている中央としては、出すぎた杭は早めに打っておかなければならないってことだと個人的には思ってます。
※上海郊外にある九年制公立学校に通う我が子の状況を元に書いた記事です。
中国全土、全上海を代表する事例ではありませんので、こんな例もあるのね、程度でお読み下さいね。




コメント