日本経済新聞国際版(日本では夕刊)にて今年の3月からスタートしていた連載小説の『つみびと』が先日エピローグにさしかかり、12月26日についに最終回を迎えました。
今日はこれまで読んできた感想として、私の想いを吐露していきたいと思います。
経緯
この小説は女性作家の山田詠美氏作の児童虐待問題を題材にした人間の深いところを描いた作品です。かつて実際に起こったある刑事事件を思わせる内容が出てきます。
これまで母・琴音、娘・蓮音(事件当事者)、小さきものたち(蓮音の子どもたち)とに分かれて物語が進んできました。
継父に性的虐待を受けたことなどを理由に心が壊れてしまった琴音。
その後結婚をして子どもを設けるも、心の傷が癒えることのないまま大きくなった琴音は、心が更に傷を負って、娘たちを置いて家を出てしまいます。
蓮音は長女として兄弟の面倒を見ながら、苦しい青春時代を過ごします。
蓮音も大人になって結婚し、子どもを2人設けますが、夫と離婚して子どもを連れて家を出ます。
その後、蓮音は子どもを家に置いて、外に出かけるようになります。
徐々に家に帰って子どもたちの世話をする頻度が減っていき、最後は家に戻ることのないまま、子どもたちは餓死してしまいます。
連鎖
琴音と蓮音に共通しているのは、
・苦しく、辛く、寂しい子ども時代、青春時代を過ごしていたこと
・父親に対して快く思っていなかったこと(琴音は虐待された)
・母親から心を救ってもらえなかったこと
・現実逃避するしかなかったこと
だったと思います。
特に、心を救ってくれる人の有無はとても大事だと思っています。
そうでないと逃げ場を失い、心が更に病み、現実逃避を考えるようになり、残された子には別の苦しみが生まれ、次の世代に苦しみが続いていきます。
蓮音の子どもたちは究極の苦しみで最期を迎えることとなりました。
虐待死という一見物事が終わったように思える出来事も、実はそれで終わりではなく、琴音や蓮音自身のみならず、彼女たちの周囲の人にとっては罰として一生続き、彼女らが亡くなっても、引き続きどこかで誰かに連鎖されていくのだなと思いました。
ふと、昔放映されていた『永遠の仔』というテレビドラマを思い出しました。
あのドラマはいろいろな虐待を受けた経験を持つ子どもが大人になってから再会し、過去のトラウマと戦いながら、癒しを求めてさまよう姿が描かれたものだと記憶していますが、登場人物の1人も、過去の傷が原因で殺人まで犯してしまうんですよね。
一方で、深い傷を負いながらも、周囲の暖かい励ましや癒しがあれば、徐々に回復していくこともできる。そんなメッセージを受けた印象があります。
因果
何事も、その「事」が起こるのには必ず原因があります。
であれば、結果は過程によってどうにでも変わっていくものだとも言えます。
この小説では、負の連鎖が子どもたちの死によって一旦区切りがつきましたが、そうなる前に誰かや何かが彼女たちの心を救っていたら、結果は変わっていたかも知れません。
時折ニュースで児童虐待事件が流れるととても悲しく思います。
私たちが生きる現実の中には事件になりそうな要素がいくつも存在していて、火が付くか付かないかのギリギリのところで保っているのだなぁと思います。
当事者にもし何かの救いがあれば、起こらなく済んでいた事件はきっと山のようにある・・・
この『つみびと』を読みながら、ずっと強く感じてきたことです。
原生家庭
虐待事件を見聞きしたり、児童虐待を取り扱った小説などを読んでいると、どうしても自分の家庭を顧みるようになります。
私が夫と築いている家庭は、果たして子どもたちにとって本当に楽しく、心から幸せを感じられる場所になっているのか。
今の家庭は、子どもたちにとって今後の人生で大きく影響を及ぼしていくであろう、根幹となる場所です。その大事な場所を私たち夫婦はうまく築いていけているのか。
中国語では自分が育った家庭のことを「原生家庭(yuánshēngjiātíng)」と言うのだそうですが、今の家で起こる様々な出来事や問題は私たち夫婦の原生家庭の影響がたくさん出てるなと思うことが多いのです。
私も夫も普通の家庭で育ってきたとは思いますが、細かいことを言い出すと、自分が育った家にもあれこれと問題があり、夫が育った家にもいろんな問題が存在していたのだなぁと感じます。
あ、もちろんいいところもあるんですが、悪いところに目が行きがちなもので。(いいところばかりに注目するともっといい家庭が築けるかも知れないですね!)
今後子どもたちが大人になって家庭を築いたとしたら、その家庭に原生家庭の跡を見ていくんでしょうね。
教え
今まで『つみびと』を読んできて、親として学ぶべきことがたくさんありました。反省することもありました。悩むこともありました。
過去形ではなく、正確には現在形ですが、しつけや教育と称する子どもへの対応が果たして本当に「教え」としての機能を果たしているのか深く考えさせられました。
単に親のうっぷん晴らしで終わっていないか、その場しのぎの対応になっていないか?
私たちの教育は、子どもの糧になっているか、傷になっていないか?
私たちは癒しを与えられているか、それとも脅威になっているのか?
100%な家庭などないとは思いますが、それでも少し上を目指して、どうしても「もっと良い」を求めてしまう。
でも、「良い」って何なんでしょう?家族でも人のものさしは全然違うのに、私の「良い」がみんなに良いとは限りません。
考えれば考えるほど深みにハマってしまいそうです。
最後のシーンに鳥肌
小説の話に戻りますが、最終回の最後の終わり方がとてもすがすがしく、鳥肌が立ちました。
琴音は女子刑務所に服役している蓮音に何度も面会の申し入れをしていて、最後に母子が再会するシーンが出てきます。
再会の場では話らしい話はできなかったのですが、面会時間が来て別れ際に蓮音は笑顔を見せ、「幸せ」と口を動かします。
自分を捨てた母とも言えないような人に向かって、「口に出して言ってみて、ママ」と促します。
それに応え、琴音もそう口にします。
幸せ。
途中の琴音や蓮音の苦しみが描かれている部分では、内容が濃い上にとても重たかったので、このような最後で小説が締められていて、なんだか心が救われたような気持ちになりました。
幸せ、か。
蓮音はどうして母にこの言葉を投げかけたのでしょうか?
いろんなことを考えさせられるとてもいい小説でした。山田さん、ありがとう。
ところで同時期に国際版に掲載されていた『愉楽にて』は既に書籍化され、重版されているそうです。
電子書籍もあります。
愉楽にて【電子書籍】[ 林真理子 ]
※2018年、日経国際版を彩った2つの小説『愉楽にて』と『つみびと』を読んだ途中経過をこちらで記しています。
※『つみびと』も待望の単行本が発売になりました!
※2019年7月追記
先般、仙台で母親による子ども置き去り致死事件が起こりました。
彼女たちを取り巻いた負の連鎖はどうして止められなかったのか。残念でなりません。
今後警察の取り調べを経て司法で裁かれると思いますが、それとは別に、彼女の生い立ちなど、この事件が起こった真の原因が研究されて、教育や社会福祉などで活かされて欲しいと思います。
こういう事件が起こるとどうしても当事者の母親だけに目が行きがちですが、周りを取り巻いていた環境にも注目すべきだと思うのです。
人の心が満たされ、救われるっていうのは、やっぱり難しいことなんですかね?虐待事件を見聞きすると、本当に残念です。

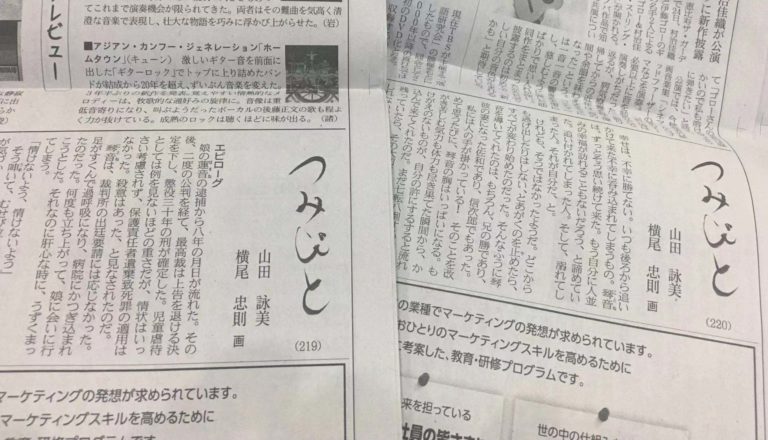

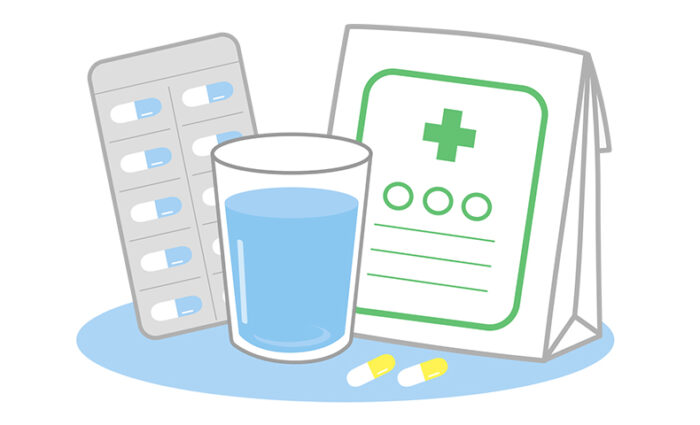

コメント
表面にあわられた事象をさわりだけ見ることでは、わからないことがあるのだと、感じる機会をいただきました。
生活保護を受ける方から金銭を不正に受け取り、衣食住の面倒を見る人がいるそうです。ところが、生活保護の方は、「居場所を与えられた気がした」と言ったと聞きました。
また、ネズミ講の団体に加入してお金を支払ったけど、母に教えてもらえなかったことすべてそこで教わったという知人がいました。
カルトと一般的に呼ばれる宗教に入信して、救われたと感じる人も確かにいるのだと思います。
家族という言葉に、バターのように塗られた良いイメージを、一旦クリーンにしてみる必要があるのだと思います。
本当にそうですね。事象の裏には見えない事情がたくさんありますね。
一般的に悪いと思われそうなことでも、それを通じて居場所を見つける人も確かにいます。
暴力団の組長さんの取材で、行き場のない人を受け入れる役割を果たしているとの発言を読んだこともありますが、物事を多角的に見ることの重要性を教えてくれた気がします。
私にとってはこの小説もそうです。